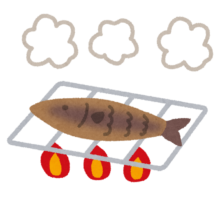2025.08.03(SUN)
食中毒について
皆さん、こんにちは! 株式会社FPOです。
8月に入り、日中は35℃以上を超える日も珍しくなくなってきました。このような気温が高い日に多く発生しやすいのがそう…食中毒です! 今回は食中毒について取り上げ、症状・予防等お伝えいたします。
食中毒とは
細菌やウイルスといった有毒な物質が付着した食べ物を食べることにより、腹痛や下痢、嘔吐などの症状が出る病気のことです。また、高温多湿の夏は細菌が増えやすくそれを原因とした食中毒が多く発生します。
食中毒の主な種類・症状
1.カンピロバクター
加熱不十分な肉類、特に鶏肉が感染源となる食中毒です。日本で発生している細菌性食中毒のなかで、近年発生件数が最も多く感染すると下痢、腹痛、発熱といった症状を発症します。
2.サルモネラ
加熱不十分な卵・肉・魚が感染源となる食中毒です。細菌を摂取してから約半日~2日後に、激しい胃腸炎、吐き気、嘔吐、下痢といった症状を発症します。
3.黄色ブドウ球菌
人の皮膚にもいる細菌で、調理する人の手や指に傷がある場合感染源となる食中毒です。細菌を摂取してから3時間前後で急激におう吐、下痢等を発症します。
4.ウェルシュ菌
人や動物の腸管や土壌など自然界に広く常在している細菌で、酸素のないところで増殖しカレーや煮魚といった煮込み料理が感染源となる食中毒です。細菌接種後6~18時間で腹痛、下痢などを発症します。
食中毒の予防
食中毒の予防の3原則として、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」があります。この3つについて下記にまとめました。
1.細菌を食べ物に「つけない」
手には様々な菌が付着しているため、それらを食べ物に付けないように調理前、おむつ交換後等には必ず手を洗います。また、生肉や魚などを切ったまな板などの器具も細菌が付着しているので使用後は洗い、殺菌します。
2.食べ物に付着した細菌を「増やさない」
細菌の多くは10℃以下では増殖が遅くなり-15℃以下では増殖が停止します。生鮮食品やお惣菜は購入後、早く冷蔵庫に入れ低温で保存することが必要です。しかし、冷蔵庫に入れても細菌はゆっくりと増殖するのでそのまま放置せず早めに食べなければなりません。
3.食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」
ほとんどの細菌は加熱によって死滅しますので、肉や魚、野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は、中心部を75℃で1分以上加熱するといった念入りに火を通す作業が必要です。
年々夏が暑くなり気温が高くなるにつれ、食中毒も発症しやすくなります。自分自身だけではなく同居の家族も発症しないよう、適切に予防していく必要があります。
厚生労働省HP:食中毒
政府広報オンライン:食中毒予防の原則と6つのポイント
農林水産省HP:食中毒の原因と種類